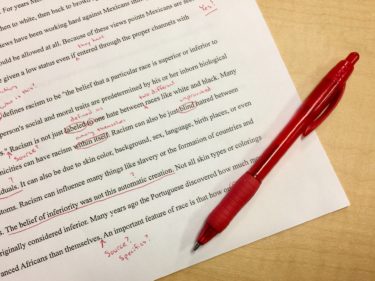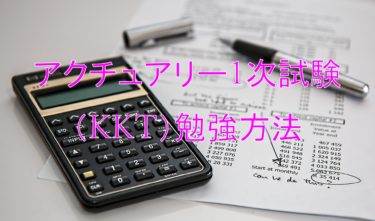「普通の人生」を送ることを希望する場合は、(男性の場合)遅くとも33歳までに正会員になりましょう!
はじめに

今までお話しした先輩方からはよく「アクチュアリー試験には早く合格しろ」と言われてきました。みなさんもきっとそうですよね?
毎回定量的・決定的な理由を合わせて言っていただいたわけではありません。正会員資格は運転免許証的な役目を果たす資格であることが理由として挙げられていたような記憶があります。
正会員になってから出来る経験もきっとあると考えられるため、アクチュアリーとしてキャリアを作るうえでも早期取得は重要だと当時も今も思います。
一方、それだけでは完全に納得できなくなってきた自分もいました。納得できなくなってきたきっかけは、先輩等から結婚・子どもの誕生の話題を聞くことが多くなったことです。
もっと自分の人生に目を向けて、試験への力加減を調節してもいいのでは・・・?とも思い始める自分もいました。
そこで自分の希望する人生(ライフステージ)を考え、 「早期取得は自分の人生に必要なのか?」「そもそも早期とはどれくらいの年齢までなのか?」に対する回答を自分の希望をもとに定量的に算出してみました。
仕事・試験・友人との遊びに追われて、普段希望する人生など落ち着いて考える余裕もありませんでした。ここで備忘録的な意味も込めて書き残したいと思います。
私の希望する人生は、「普通の人生」です。次節では、「普通」の意味をもう少し定量化して、解答の説明をしたいと思います。
試験へのモチベーション維持のために参考になれば幸いです。
希望する人生に基づいた考察
「普通の人生」の定量化
「普通の人生」の定性的な説明(※あくまで私個人の希望です)
- ライフステージ推移は、一般的なもの((交際⇒)結婚⇒子育て⇒老後など)を想定
- 第一子誕生までに正会員になりたい(子育てに時間を割きたいため)
定性的な説明に基づく「普通の人生」の定量化
- ライフステージ変化のタイミングは、現状の平均とする
- ライフステージは、大学卒業(入社)・交際・結婚・第一子誕生を考える
- 現状の平均は、厚労省の「人口動態統計」や「出生動向基本調査」を参考にする
- 試験合格までの年数は、アクチュアリー会HPで公開されている8年(準会員まで5年、正会員まで3年)とする
- 正会員達成(全科目合格)は第一子誕生と同タイミングとする
定量化した「普通の人生」年表および結論
定量化した前提を踏まえた「普通の人生」年表は下記のとおりです。
正会員になるタイミングを第一子誕生と同タイミングとして「普通の人生」を送る場合、受験期間は最大13年間しかありません。入社後に限ると、9~11年間です。
下記年表から、「普通の人生」を送るためには33歳までに正会員になる必要があることがわかります。

※結婚・交際開始年齢は、厚労省の「出生動向基本調査」を参考に平均年齢を参照
※退職年齢、年金受給開始年齢は、一般的に考えられる最も若い年齢を入力
※参照した平均年齢は、適宜四捨五入を行っている。
もちろんこの年表は、あくまで私の希望する「普通の人生」に基づいて作成したものです。必ずしもこの通りに生きなければならないというものではございません。
例えば会社での昇進を目指す人生を送りたいのであれば、これよりさらに早く正会員になり様々なキャリアを積むことも考えられます。転職を前提とした人生を考える場合でも同様と思います。
自分自身の送りたい人生を定量化しながら、各々に正会員になりたいタイミングを考えてみてください。
結論を踏まえた今後の方針、感想など
個人的な感想をリスト形式でまとめました。みなさんはどのような感想を持たれましたか?
- 受験期間に余裕が殆どないため、試験はとにかく早く合格する必要がある。第一子誕生までに限ると、受験期間が約10年前後しかないことに焦りを覚えた。
- 試験以外にも遅れている箇所があるため、プライベートも一定充実させる。
→時間の確保が最優先- 業務等の効率化・削減を必要な手順を踏んで提言し、業務時間を削減
- 自分自身の趣味を一定控えて時間を捻出する
- 一方で業務量や自身の健康状況より満足いく勉強量が確保できず合格が難しい年もあると考えられることから、数年程度は柔軟にスケジュールを組み替えることも最終手段として考える。
- 特に今年は色々な面で勝負の年にと考えられるため、後悔ない一年を過ごしたい。
おわりに
昨年は、肉体的には楽になったものの精神的に辛い場面が多く試験勉強に身に入らないことが多かったです。また初の二次試験ということもあり、勉強方法の確立もうまく進まず苦しさを感じていました。
一方で自分に合う勉強法の手がかりも見つけられたので、来年は自分の希望する人生が送れるよう実りある一年にしたいです。
みなさんも、合格発表までのこのタイミングを使って自分の希望する人生を考えながら、長期的な目線で試験勉強への力の入れ具合を考えてみてはいかがでしょうか。