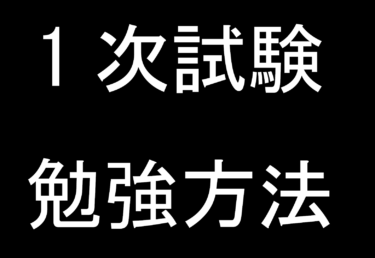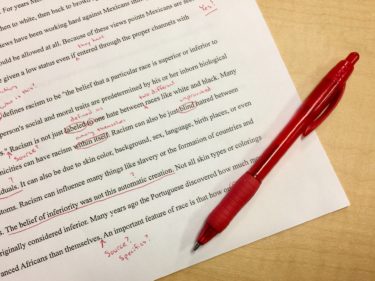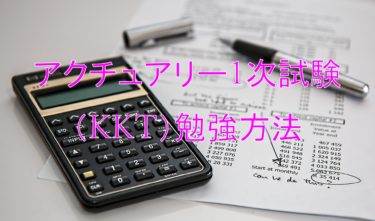はじめに
1次試験損保数理で私が行った勉強方法やスケジュールについて記載します。今後受験される方の参考になれば幸いです。当記事は、以前執筆した以下の記事の内容が前提となっている箇所がございますので、未読の方はこちらからお読みください。
はじめに ポイント!・勉強方法は十人十色、他者の方法は参考情報・当記事で紹介する方法は執筆者にハマった方法・未合格の人は、色々な方法を試して自分にハマる勉強方法を見つけよう 今回はアクチュアリー1[…]
損保数理を受験するにあたっての注意事項

損保数理を受験するにあたって、事前に知っておいたほうがよい事柄をお伝えします。
非常に難易度が高い
教科書の内容もさることながら試験の難易度がかなり高いです。1次試験の関門と言われることが多いです。そのため、損保数理に合格すると準会員おめでとうと言われることもしばしばです。
ほぼ毎年新問がでる
そもそも非常に難易度が高い一方で、ほぼ毎年新問が出ます。これをどこまでさばけるかが合否に関わってきます。
計算が異様に大変
1次試験の中で計算が突出して大変です(最近では数学でも大変ですが・・・)。答えが瞬時に出せる公式などを何個も暗記しておく必要があります。
合格率にブレが少なく基本的に低い
非常に難易度が高いこともあってか、合格率は毎年低いです。いい意味では安定していると言えます。合格率は良いときで20%程度でしょうか。
スケジュール、勉強方法
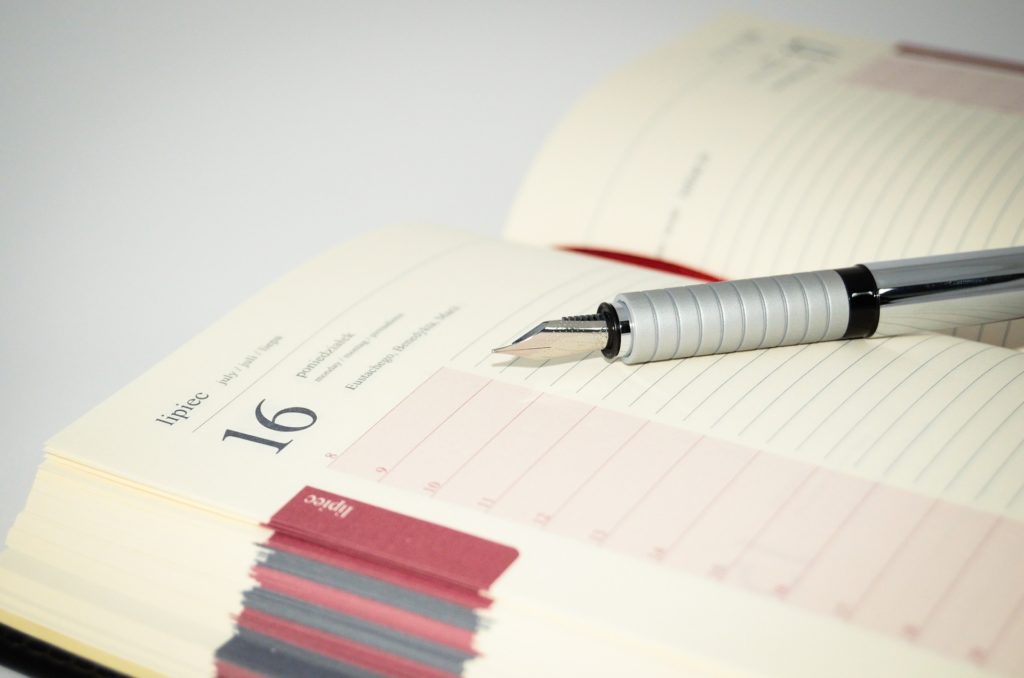
スケジュール
勉強1年目
- 5月中旬~8月末:教科書中心の勉強
- 8月末~9月末:教科書の進みが思ったより悪く、勉強を断念
- 9月中旬~試験当日:同時受験の数学に注力し、まったく勉強せず試験本番を迎える
勉強2年目
- 合格発表~4月末:充電期間(勉強していなかった)
- 5月~8月末:教科書の再読、アクチュアリー受験研究会のワークブックを用いた演習
- 8月末~試験当日:過去問10年分2,3周+合格へのストラテジーの公式全暗記
勉強方法
1年目の勉強方法
5月中旬~9月末の勉強方法
この期間は教科書を用いた勉強をしていました。教科書を読み進めるのですが、初学だったこともあり、全く理解ができず進捗が非常に遅れていました。そのため、9月末時点で演習が不十分になるどころか、教科書すら読み切れないと考え、同時受験の数学に注力することとしました。2年目を迎えるまで一切勉強しませんでした。
2年目の勉強方法
5月~8月末の勉強方法
合格発表以降はイベントごとが多く(言い訳ですが)、試験勉強に手を付けることができず、5月からのスタートとなりました。5月から8月末まで教科書を読み進めながら、アクチュアリー受験研究会のワークブックを解き進めていました。教科書は1年経過していることもあってか、なぜか自明に思えることが増えており、サクサク読み進めることができました。ワークブックを1周した時点で、過去問演習へ移りました。
- (補足)アクチュアリー受験研究会のワークブック
アクチュアリー受験研究会員であればだれでも使用できる冊子です。いわばアクチュアリー試験の「チャート式」であり、分野ごとに過去問がまとまっています。教科書の章に合わせて演習を行うことが可能です。
8月末~試験当日
ひたすら過去問演習と発売された合格へのストラテジーの公式集全暗記を繰り返し行っていました。過去問は他科目と同様2時間で90点取れるレベルまで仕上げた記憶があります。
受験歴(申し込み歴)
1回目(実質記念受験):不合格III
2回目:合格
使用書籍
使用書籍は、教科書と合格へのストラテジーと過去問です。「例題から学ぶ損保数理」は購入はしましたが、結局使いませんでした。
参考サイトなど
損保数理も特段参考サイトはありません。
試験本番時のメンタルなど

1年目の本番中のメンタル
完全にあきらめている中での記念受験だったので、緊張も何もありませんでした。しかしながら、どうやらその年度は普段よりも簡単だった?らしく、勉強しなかったことを少し後悔しました。
2年目の本番中のメンタル
実質初受験で合格も難しいと感じていたので、そこまで緊張していませんでした。当日前半はいいペース(30点強程度確保?)で解き進められたものの、後半から難易度が急に跳ね上がり(自分比)焦り始めました。
焦りはしましたが、考えても解法は出てきませんでした。一方で公式丸暗記で解答できる問題がいくつもあり、「5の(1)(2)は解けないけど、(3)以降は全部解ける」といったラッキーが発生しました。その結果、試験後は50点強でボーダーくらいかなあという感触でした。
おわりに

生保数理が不合格であった一方、損保数理は実質初受験で合格することができ、先輩方に褒められました。一方で、もう準会員だねとプレッシャーをかけられることとなりました・・・。公式暗記に非常に救われた試験になりました。